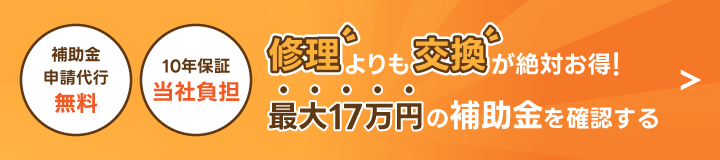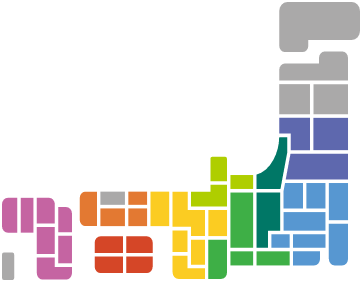昔は「混浴」が当たり前だった!?驚きだらけの「日本の風呂文化」の歴史
現代において、風呂は住まいの必須設備と言っても過言ではなく、また日本人は世界的に見ても風呂をこよなく愛する民族だと言われています。
また地理的な面でも、火山国である日本では全国各地で様々な温泉が湧き出ています。
そんな日本における風呂の歴史はいつ始まり、いつ今のカタチとなって浸透したのでしょうか。
今回は時代ごとの風呂事情を探りながら、日本の風呂文化への理解を深めていきたいと思います。
日本の風呂文化の起源

前述したように日本では古くから各地で天然の温泉が湧き出ており、人々は野湯や岩風呂(岩穴をくり抜いたり、石を積み重ねて造った空間で行う蒸気浴)に入浴していたそうです。
「入浴」の概念自体が広まったのは、6世紀に中国から仏教と共に伝わってきたのがきっかけだと言われています。
仏教において、風呂に入ることは「七病を除き、七福が得られる行為」と説かれていたため、当時から既に入浴は健康に良い行為だと解釈されていました。
それ以来、寺院には「心と体の垢を落とす」という大切な修行を行うための空間として浴堂が備えられるようになりました。
また、奈良時代以降は貧しい人々に向けて寺院の浴堂を開放する「施浴(せよく)」がさかんに行われるようになり、庶民に入浴の良さが広まるきっかけとなりました。
鎌倉・室町時代の「風呂ふるまい」

奈良時代に始まった施浴の習慣は、鎌倉時代になっても続きました。
鎌倉時代の歴史書である『吾妻鏡』には、源頼朝が鎌倉山内の浴堂で行なった100日施浴や、幕府が北条政子の追善供養のために行なった長期間施浴のことが記されています。
室町時代になると施浴は「功徳風呂」と呼ばれるようになり、日程を予め定めた上で庶民にふるまわれるようになりました。
やがて施浴の習慣は幕府や寺院にとどまらず、庶民にも浸透していきます。
室町幕府第8代将軍・足利義政の正室だった日野富子は、毎年末になると両親追善供養のための施浴を催し、親類縁者たちを招待しました。
その際、風呂だけではなく食事もふるまったそうです。
この頃から、庶民階級でも風呂がある裕福な家では客人を招待して風呂をふるまい、入浴後には茶、酒、ごちそうなどを用意して楽しいひとときを過ごすことが習慣化していきました。
これが、いわゆる「風呂ふるまい」です。
同じ頃、地方では村内の仏堂に信者が集い、風呂をわかして入り、入浴後は各自持ち寄った酒や肴をあてに宴を催す「風呂講」もさかんに行われていました。
江戸時代に生まれた「銭湯文化」
 寺院の浴堂や風呂ふるまいではなく、純粋な公衆浴場としての「銭湯(湯屋)」文化が誕生したのは、江戸時代に入ってからです。
寺院の浴堂や風呂ふるまいではなく、純粋な公衆浴場としての「銭湯(湯屋)」文化が誕生したのは、江戸時代に入ってからです。
当初の銭湯は、ほとんどが蒸し風呂の一種である「戸棚風呂」形式でした。
戸棚風呂とは、湯船に少量の湯を入れて下半身は湯に浸かり、上半身は蒸気浴するという仕組みになっている風呂のことです。
蒸気が逃げないように湯船についた引き戸を閉める形式が戸棚に似ていることから、この名前で呼ばれていたそうです。
とはいえこの戸棚風呂は、頻繁に引き戸が開閉されるとどうしても蒸気が逃げてしまいます。
そこで誕生したのが、「石榴(ざくろ)口」付きの風呂です。
石榴口とは、浴槽の前方上部を覆う仕切りを取り付け,客がその下をくぐり抜けて浴槽に入るようにした入口のことです。
湯が冷めないよう狭い入口となっているのが特徴でしたが、明治以降は「不衛生である」として銭湯への石榴口の導入は禁止されました。
また、江戸の銭湯は「入込(いりこみ)湯」と呼ばれる男女混浴スタイルが一般的でした。
しかし多くの人は純粋に入浴を楽しむ一方で、やはり風紀を乱す者も少なくなかったようで、度々幕府は混浴禁止令を出していました。
それでも一向に入浴形態が変わることはなかったのですが、江戸時代後期の厳格な老中として知られる水野忠邦が起こした天保の改革(1841~43)によって、ついに具体的な取り締まりが行なわれることになります。
これ以降、江戸の多くの銭湯は浴槽の中央に仕切りを作ったり、入浴日時を男女で分けるなどの対応に取り組みました。
また、男湯のみ、女湯のみという銭湯も出てきたそうです。
明治時代に入ると混浴に対する取り締まりは一層厳しいものとなり、明治政府は男女入込湯に度々注意喚起を行いました。
しかし、長い年月の中で根付いた風習を消し去るのはなかなか難しく、実際に混浴が無くなったのは、明治中頃だったと言われています。
「家風呂」の普及

慶長時代末期ごろになると、蒸し風呂に代わりにたっぷり溜めた湯に全身で浸かる「据え風呂」が普及し始めます。
一般の庶民の家庭にも入浴の習慣が広まったのは、据え風呂の登場がきっかけだと考えられています。
当初は既に沸かしておいた湯を風呂桶に入れる方法が主流でしたが、その後風呂桶の中に鉄製の筒を取り付け、そこに燃えている薪を入れて湯を沸かす方法が発明されます。
この入浴方法は「鉄砲風呂」と名付けられ、江戸を中心に広まりました。
一方その頃関西では、風呂桶の底に設置した鉄製の平釜を使って湯を沸かす「五右衛門風呂」が主流となっていました。
明治時代の風呂文化

明治時代以降、銭湯の在り方は急激な変化を遂げることになります。
石榴口は撤去され、蒸し風呂式はほぼ廃止となり、浴槽にたっぷり湯を溜める据え風呂形式が主流となりました。
また洗い場は広く天井は高くするなど、今までの「銭湯=手狭で薄暗い空間」という印象を拭い去るような開放的で清潔感のある空間へ改良する銭湯も続出し、大いに評判となりました。
大正時代になると銭湯の近代化はさらに進み、洗い場や浴槽は木製に代わってすべてタイル張りとなりました。
水道が普及してからは浴室に水道式のカランが取り付けられ、衛生面も格段に向上しました。
そして銭湯の発展を追うように、家風呂へのタイルや水道式カランの導入も急速に進められていったのです。
現代日本における風呂

戦後、欧米文化が庶民の間に浸透し始めると、現代のスタイルに近い「家風呂」が各地に普及していきます。
電気・ガスが発達して以降は、追い焚き機能、温度自動調節機能、乾燥機能の搭載など、性能面でも飛躍的な進化を遂げています。
それだけではなく、ジャグジー、水中照明、テレビやラジオ付きなど、入浴をエンターティメントとして楽しめる機能を備えた家風呂も登場しています。
また、近年ではバスタイムを癒しの時間にしてくれるバスソルトや入浴剤も充実しています。
また、度々到来する「サウナブーム」や「岩盤浴ブーム」などの影響もあり、現代の温泉やスーパー銭湯は老若男女問わず多くの人に愛される存在となっています。
今後も何度かブームを繰り返しながらも、温泉や銭湯は人々の癒しと憩いの場で在り続けることでしょう。
まとめ
今回は、日本における風呂文化の歴史について紹介していきました。
こうして歴史を振り返ってみると、自宅に風呂設備があって毎日入浴できることは、とても贅沢なことなのかもしれないと思えてきますね。
また、日本ではただ体を清潔に保つために入浴するのではなく、楽しむために温泉に行ったり自宅でのバスタイムを工夫する人が多い点を見ると、やはり日本人は入浴が大好きなのだということが分かります。
当社では、そんな入浴を支える給湯システムのエコキュートを主に取り扱っています。
「今使っているエコキュートよりも給湯効率の高い機種に交換し、エコなバスタイムを過ごしたい」という方は、是非当社までお気軽にお問い合わせください。