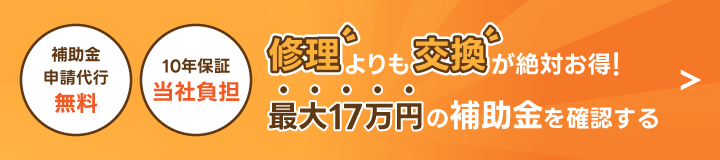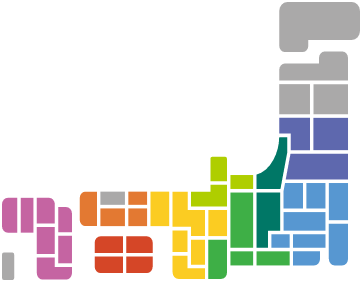初めてでもできる!?エコキュートの水抜き方法や注意点等を解説
エコキュートの水抜きは、忘れてはならないメンテナンスの一つです。
しかし、中には購入してから一度も水抜きをしたことがないという方もいらっしゃるでしょう。
これまでとくにトラブルが発生していなくても、知らずにトラブルの原因を作ってしまっているかもしれません。
そこで今回は、エコキュート水抜きの重要性についてお話しします。
水抜きのメリットや手順、注意点などについても詳しく解説していくので、ぜひチェックしてみてください。
エコキュートの水抜きが必要な理由
エコキュートの水抜きが必要になるのは、主に4つの理由があります。
- 貯湯タンク内に不純物が溜まる
- 浴槽に汚れが浮く
- お湯に黒いゴミが混ざる
- エコキュートの寿命が短くなる
貯湯タンク内に不純物が溜まる
エコキュートは、貯湯式の電気温水器です。
ヒートポンプユニットで沸かしたお湯は、一度貯湯タンクに貯める必要があります。
使用する水道水は衛生的ですが、ナトリウムやカルシウム、カリウムなどを始め、ごくわずかな不純物が含まれています。
そのため、水抜きをおこなわないと、不純物が貯湯タンクの内部に溜まって沈殿してしまうのです。
水抜きをすることで貯湯タンク内に溜まった不純物が排出され、より清潔な水を使えるようになるでしょう。
浴槽に汚れが浮く
長い期間水抜きされないと、貯湯タンクの不純物は固まった汚れとなり、お湯張りの際に流れ込むことがあります。
フィルター詰まりの原因になることも、浴槽に浮いて不潔に見えることもあるでしょう。
また、排水溝のような嫌な臭いを感じることもあるかもしれません。
新しくお湯を張ったのに、湯垢のようなものが浴槽に浮いていたり、何だか嫌な臭いがしたり……といったトラブルが起こる前に、定期的に水抜きをしてください。
エコキュートの故障を疑うような状況であっても、水抜きをしただけで、一気にトラブルが解決したというケースもあります。
お湯に黒いゴミが混ざる
エコキュートを設置してから年月が経過すると、製品そのものに問題はなくても、内部のパーツは確実に劣化していきます。
とくに配管の接続部分に使われているゴムパッキンは、素材の性質上、経年劣化しやすいパーツです。
ゴムパッキンが劣化すると、一部が剥がれ、お湯の中に黒いゴミとして混ざることもあります。
これも水抜きをして貯湯タンク内の清掃をおこなうことで、ゴムパッキンから出た黒いゴミを取り除けるでしょう。
エコキュートの水抜きをしても黒いゴミが混ざってしまうようであれば、ゴムパッキンの劣化が進んでいるということですので、パーツ交換が必要になるケースもあります。
また、寿命の目安とされている10年ほどを経過しているならば、エコキュート本体そのものの交換を検討しても良いタイミングかもしれません。
エコキュートの寿命が短くなる
不純物や汚れが含まれた水は、浴槽のフィルターを詰まらせる原因になります。
循環口に取り付けられたフィルターは、浴槽内のお湯も循環するため、皮脂汚れのような浴槽内の汚れも溜まりやすい箇所です。
風呂配管(追い焚き配管)から貯湯タンクへは逆流しないため、貯湯タンク内まで汚れるような事態にはなりません。
しかし、フィルターが詰まるとお湯の出入り悪くなり、エコキュート本体に負担がかかります。
たかが水抜きやフィルター掃除と思いがちですが、それがエコキュート本体の寿命を短くするリスクや、故障原因につながってしまうのです。
また、稼働効率も悪くなるため、電気代が余計にかかる恐れがあることも心配しなければなりません。
汚れにより部品が劣化する
水抜きをしないままでいると、汚れによって配管などの部品が劣化することがあります。
貯湯タンク内の湯垢や沈殿物は、ふろ配管へ流れ、循環口のフィルターに詰まってしまうためです。
詰まりによってお湯が上手く循環しなくなれば、エコキュートに負担がかかり、やがて部品の劣化を招きます。
エコキュートが故障する原因にもなり得るため、水抜きは定期的におこなう必要があります。
エコキュートの水抜きが必要なタイミング
エコキュートの水抜きは、どのようなタイミングで行えばよいのでしょうか。主に3つのタイミングがありますので、それぞれ解説します。
エコキュート水抜きの頻度は半年~1年が目安
エコキュートの水抜きは、半年~1年に一度が目安です。
循環口に取り付けられたフィルターと違い、貯湯タンクや配管といった内部は目視できず、どの程度汚れているか確認できません。
しかし放置すれば、知らず不衛生なお湯を使うことになったり、エコキュートの寿命を縮める要因になったりします。
そのため、定期的におこなう習慣をつけるのがお勧めです。
「夏季休暇や年末年始等にはエコキュートの水抜きをおこなう」といった計画をぜひ練ってみましょう。
忘れるかもしれないと不安な人は、カレンダーに水抜き予定日を記載したり、アプリのスケジュール機能で管理したりといった方法を試してみると良いかもしれません。
浴槽に黒い汚れが出るとき
「ふろ配管から黒い汚れが出てくる…」というようなときも、水抜きをすべきタイミングといえます。
黒い汚れは、ふろ配管の汚れや部品の劣化によっても生じますが、貯湯タンク内の汚れが出ている可能性もあります。
一度、ふろ配管の掃除と貯湯タンクの水抜きをおこない、それでも黒い汚れが出てくるようであれば、業者に見てもらうのがお勧めです。
水道が断水したとき
エコキュートの水抜きは、水道が断水したときにも推奨されています。
断水が解除された後は、しばらく汚れた水が出てくることがあります。
貯湯タンク内に汚れた水が入ると、綺麗なお湯が使えないだけでなく、詰まりや故障の原因になります。
断水に備えて、あらかじめ貯湯タンクの給水元栓を閉めていた方は不要です。
しかし、貯湯タンク内に汚れた水が入ってしまったのであれば、水抜きをすると良いでしょう。
エコキュートの水抜きをするメリット

「そうとは言っても、「メンテナンスは面倒くさくて…」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、エコキュートを水抜きすることには、多くのメリットがあります。ぜひ実施してみてください。
エコキュートをより長く使える
水抜きをすれば、エコキュートをより長く使い続けられる可能性が上がります。
エコキュートの寿命は10~15年ほどと言われていますが、適切に使用しなければ当然短くなります。
水抜きを始めとする適切なメンテナンスをすれば、費用をかけて購入したエコキュートの寿命を延ばし、より長く使えるでしょう。
お湯に汚れや不純物が混ざらない
エコキュートの水抜きを定期的におこなえば、お湯に汚れや不純物が混ざるのを防げます。
洗面所や浴室、台所等で使うお湯に、汚れや不純物が混ざっていると、使うことに抵抗感が生まれるはずです。
定期的に水抜きをおこなっていれば、いつでも清潔なお湯が使えます。
顔や体を洗うお湯が清潔であれば、心地良く洗顔やバスタイムを楽しめ、リフレッシュにつながるでしょう。
長時間使用しない場合は凍結対策に
エコキュートを長時間使わない場合は、水抜きが冬場の凍結対策にもなります。
旅行や出張等、家を空ける場合には、ほとんどの方はエコキュートを使用しなくなります。
その際、水が残されていると、貯湯タンクや配管の中で凍結するおそれがあります。
凍結した水は膨張するため、配管や貯湯タンクに傷が付いたり破損したりということが起こり得ます。
長時間使用しない場合には、水抜きをしておくのがお勧めです。
非常時に生活用水として使える
貯湯タンク内の水は、非常時に生活用水として使えます。
手洗いや洗濯、トイレ等で使用する生活用水は、非常時ほど貴重です。
そのままでは飲用できませんが、いざとなれば沸かして飲めます。
しかし、お湯が汚れていたり、不純物が混ざっていたりすれば、飲むことはできません。
万が一の際に備えて、貯湯タンク内をできるだけ清潔に保つことが大切です。
エコキュートの水抜き手順
次にエコキュートの風呂配管・貯湯タンクユニットの洗浄・水抜きの手順をご紹介します。実際に水抜きを行う際は、必ず、説明書やメーカーのホームページを参照しながら行ってください。
自分でできるか心配な方は、有料にはなりますが、メーカーの「貯湯タンク清掃サービス」や、業者への依頼を検討してみましょう。
事前準備と用意する道具
水抜きに必要な道具は、下記の通りです。
・ドライバー(マイナスドライバー、プラスドライバー)
・手を保護するもの(軍手、ゴム手袋等)
貯湯タンクのふたや脚部カバー等を取り外す際には、ドライバーを使用してネジを外します。
作業時の怪我を防ぐため、また、ネジが潰れないようしっかり手で固定するためにも、軍手やゴム手袋等、手を保護するものも用意してください。
水抜きにかかる時間
水抜きそのものにかかる時間の目安は、下記の通りです。
・貯湯タンク底の汚れや沈殿物を排出する場合…約1~2分
・水を全て排出する場合…約1時間~1時間半
貯湯タンク底の汚れや沈殿物を取り除くための簡単な水抜きなら、1~2分程度で十分です。
上記は、水抜きそのものにかかる時間のため、作業時間はプラス15~30分ほどと考えて水抜きをおこなってみてください。
ただ、長期的にエコキュートを使わない場合、使っていなかった場合は、貯湯タンクや配管から水を全て排出する本格的な水抜きが必要です。
作業や作業時間については、メーカーや機種等で大きく変わるため、メーカーホームページや取扱説明書を参考にしてください。
貯湯タンクユニット内部の洗浄・水抜き基本手順
貯湯タンクの水抜きは、エコキュートの周りで作業する必要があります。
プラスドライバーやマイナスドライバーなどが必要になるため、あらかじめ用意しておきましょう。
メーカーホームページや取扱説明書も確認しながら、おこなってみてください。
※貯湯タンク下部の、脚部カバーは取り外した状態で作業を行ってください。
- 貯湯タンクの「漏電遮断器(漏電ブレーカー)」をオフにします。
※機種によって取付箇所が違うので、取扱説明書をご確認ください。 - 給水配管の途中についている「給水側止水栓」を閉め、万が一の際に放水しないようにします。
- 貯湯タンク上部の点検口(逃し弁カバー)を開け、中の「逃し弁レバー」を手前に起こしてください。
- 「排水栓」を開いて、2分ほど水を出し続けタンクの汚れを流します。
- 排水後、「排水栓」を閉じます。
- 「給水側止水栓」を開きます。
- 排水口(排水ホース)から、水(お湯)がしっかりと出ることを確認します。
※空気が混じっていないか確認してください。 - 「逃し弁レバー」を元に戻し、「漏電遮断器(漏電ブレーカー)」をオンにします。
- 各カバーを取り付け直して完了です。
作業中に勢いよく水が飛び出すことがあり、慌てるかもしれません。
しかし、この水の勢いで沈殿した不純物や汚れを取り除くので、排水栓の開き具合を調整する必要はありません。
こちらも風呂配管の水抜き同様、自分でできるか心配な方は、メーカーの「貯湯タンク清掃サービス(有料)」や、業者への依頼を検討してみましょう。
メーカー別手順
水抜き手順を、メーカー別に見ていきます。
なお、手順は、脚部カバーの有無や機種等によって異なることがあります。
メーカーホームページや取扱説明書も確認しながら、年に2~3回を目安におこなってみてください。
説明書がない場合は、以下のリンク先も確認してみてください。
| パナソニック | 【エコキュート】 タンク(貯湯ユニット内)のお手入れについて (動画説明あり) |
|---|---|
| 三菱 | 取扱説明書 P.21 |
| ダイキン | 知っておきたいエコキュートのお手入れ |
| 日立 | 取扱説明書 P.50 |
| 東芝 | 東芝ヒートポンプ給湯機(家庭用) 取扱説明書 P.12 |
| コロナ | 取扱説明書のダウンロード |
次に、各メーカーのホームページや説明書を参考に、手順をまとめています。
実際に水抜きを行う際は、必ず、ホームページや説明書を参照しながら行ってください。
パナソニック
パナソニックエコキュートの水抜きは、主に下記の手順でおこないます。
- 浴そうを空にし、追い炊きをしてふろ配管に残った水を抜く。
- 2020年以降のモデルの場合、台所リモコンのメニューからタンク水抜き設定を選んで行う。約10分後、設定が解除されたら次へ。
- 残湯量が減っていることを確認する(※安全のため、少なくとも残湯量が1以上減っているときにおこなう)
- 下側のふたを開き、配線用しゃ断器(ブレーカー)と漏電遮断器をオフにする
- 脚部カバーを取り外す
- 混合水栓のお湯側と水側を開き、お湯が出なくなるまで出す。
- 混合水栓の水側と、給水元栓を閉める
- 上側のふたを開き、逃し弁レバーを上げる
- 排水栓を開き、排水する
- 混合水栓のお湯側を閉じる
- 貯湯ユニットの5か所すべての水抜き栓と非常用取水栓をゆるめ、屋内用の水抜き栓1か所ははずす
- ヒートポンプユニットの水抜き栓(3か所)をゆるめる
- 水が出なくなるまで放置する
- すべての水抜き栓と非常用取水栓を閉じ、ストレーナーと屋内用の水抜き栓1か所を取り付ける
- ヒートポンプユニットの水抜き栓(3か所)を閉じる
- 排水栓を閉じる
- 逃し弁レバーを元に戻し、上側のふたを閉じる
- 漏電遮断器をオンにし、下側のふたを閉じる
- 混合水栓を開き、お湯が出ることを確認
- 脚部カバーを取り付ける
三菱
三菱エコキュートの水抜きは、主に下記の手順でおこないます。
- 操作窓を開け、電源レバーを「切」にする
- 脚部カバーが付いている場合は、脚部カバーを外す
- 給水配管専用止水栓を閉じる
- 逃し弁操作窓を開けて、逃し弁のレバーを手前に起こす
- 排水栓を約1~2分間開き、タンクの下部にたまった水あかを排水する。排水ホッパーから排水があふれないように排水栓を調整する
- 約1~2分間たったら、排水栓を閉じる
- 給水配管専用止水栓を開き、排水口から勢いよく水(湯)が出るまで待つ
- 逃し弁のレバーを戻す
- 脚部カバーを取り付け、電源レバーを「入」にする
ダイキン
ダイキンエコキュートの水抜きは、主に下記の手順でおこないます。
- 下側の点検口を開き、漏電遮断器をオフにする
- 脚部化粧カバーを取り外す
- 給水止水栓を閉める
- 上側の点検口を開き、逃し弁レバーを上げる
- 排水栓(薄型は2箇所)を「排水」に合わせて約2分排水する
- 排水栓を元に戻す
- 給水止水栓を開ける
- 黒い排水ホースから、お湯が連続して出てくるまで待つ
- 逃し弁レバーを戻し、上側の点検口を閉じる
- 漏電遮断器をオンにし、下側の点検口を閉じる
- 脚部化粧カバーを取り付ける
日立
日立エコキュートの水抜きは、主に下記の手順でおこないます。
- 漏電遮断器のスイッチ(電源スイッチ)を「OFF」にする
- タンク専用止水栓を閉じる。水道直圧給湯フルオート(ナイアガラ出湯)の場合、タンク専用止水栓は開いたままにする
- 逃し弁のレバーを上げる。水道直圧給湯フルオート(ナイアガラ出湯)の場合、操作の必要なし
- タンク排水栓のハンドルを右側に回し、約2分間排水し、元の位置に戻す
- タンク専用止水栓を開ける。水道直圧給湯フルオート(ナイアガラ出湯)の場合、操作の必要なし
- タンク排水管からお湯が出てきたら、逃し弁のレバーを下げる。水道直圧給湯フルオート(ナイアガラ出湯)の場合、操作の必要なし
- 漏電遮断器のスイッチ(電源スイッチ)を「ON]にする
東芝
東芝エコキュートの水抜きは、主に下記の手順でおこないます。
- 残湯量が3メモリ以下、あるいは湯張りをした後であることを確認する
- 脚部カバーを取り外す
- 給水止水栓を閉める
- 電源扉を開け、漏電遮断器をオフにする
- 逃し弁扉を開け、逃し弁レバーを上げて約1分待つ
- 排水栓扉を開け、排水栓を左に回して約2分待つ
- 排水栓を右に戻す
- 排水が止まったことを確認したら、給水止水栓を開く
- 排水トラップにお湯が出てきたら、逃し弁レバーを下げる
- 漏電遮断器をオンにし、電源扉と逃し弁扉、排水栓扉を閉じる
- 混合水栓を開き、お湯が出ることを確認する
- 脚部カバーを取り付ける
コロナ
コロナエコキュートの水抜きは、主に下記の手順でおこないます。
- 漏電遮断器操作カバーを外し、漏電遮断器の電源レバーをオフにする
- 脚カバーを取り外す
- 給水専用止水栓を閉じる
- 逃し弁操作カバーを外し、逃し弁レバーを上げる
- 排水栓を開く(300Lタイプは、排水栓操作カバーを外してください)
- 約1~2分後、排水栓を閉じる
- 給水専用止水栓を開く
- 排水口から水が出たことを確認したら、逃し弁のレバーを下げ、逃し弁操作カバーを取り付ける
- 漏電遮断器の電源レバーをオンにし、漏電遮断器操作カバーを取り付ける
- 脚カバーを取り付ける
- 日時設定や給湯・風呂温度設定等が変わっていたら元通りにする
水抜きの他に自分でできる掃除・点検
水抜き以外にできる掃除や点検、お手入れ方法はいくつかあります。実際に掃除や点検などを行う場合は、安全のためにも、メーカーのホームページや説明書を参照しながら行ってください。
ふろ配管の掃除
水抜きをするのであれば、ふろ配管の掃除も併せておこなうとよいでしょう。
ふろ配管は、貯湯タンクユニットと浴槽を直接つなげている配管を指します。
浴槽にお湯を供給する他、フルオートタイプでは追い焚き機能でお湯を循環させているため、配管内部は汚れてしまいます。
自動配管洗浄機能が付いているエコキュートであっても、時折は掃除をおこなうことが推奨されています。
ふろ配管の掃除方法は、下記の通りです。
- 自動運転を切り、循環口から10cmほど上までお湯や水を張る
- 浴槽にメーカー推奨の洗浄剤を溶かす
- リモコンを操作して「ふろ配管洗浄」をおこなう(※メーカーによっては「配管洗浄」や「循環洗浄」等、名称が異なります)
- 配管の洗浄中を示す表示がリモコンから消えたら、浴槽のお湯を抜く
- 浴槽の掃除をおこなう
- 浴槽や配管をすすぐために、1~3をおこなう
フィルターの掃除
浴槽に取り付けられているフィルター(循環口フィルター)も、ぜひ掃除したい部分です。
ふろ配管とつながる浴槽の循環口には、フィルターが取り付けられています。
フィルターは汚れを受け止める部品で、皮脂や埃、石鹸や入浴剤等、様々な汚れが蓄積する場所です。
フィルターを取り外し、風呂掃除用のブラシや、不要になった歯ブラシ等を使用して、汚れをこすり落としてください。
循環口も、溝や穴等に汚れが詰まっていることがあります。同様にブラシで掃除し、フィルターを戻せば完了です。
漏電遮断器・逃し弁の点検
水抜きとまとめてできるため、水抜きの際に漏電遮断器と逃し弁の点検もおこえるとよいでしょう。
漏電遮断器は、漏電や短絡(本来流れるべきでない場所に大きな電流が流れること)、過電流(想定を超えた電流が流れること)等が起きた際に、自動で電源をオフにしてくれる機能を持っています。
一方、逃し弁は、エコキュートが沸き上げる際に膨張したお湯を排出し、圧力を調整する機能を持っています。
点検は、下記の手順でおこなうことができます。
- 貯湯タンクユニット下側のふたを開け、テストボタンを押す
- 漏電遮断器をオフになることを確認したら、漏電遮断器をオンに戻し、ふたを閉じる
- 貯湯タンクユニット上側のふたを開け、逃し弁レバーを上げる
- 排水口からの排水が確認できたら、逃し弁レバーを戻し、ふたを閉じる
テストボタンを押して漏電遮断器がオフになり、逃し弁レバーを操作して排水ができていれば、動作は正常です。
正常に動作しない場合は、業者に問い合わせ、修理や交換を依頼してみてください。
エコキュートの水抜きに関する注意点

作業は明るい時間帯におこなう
作業を安全におこなうためにも、水抜きは明るい時間帯に開始してください。
例えば、濡れた手で漏電遮断器を操作すると、感電の危険があります。
他にも、配管から水漏れをしている場合に見過ごしてしまったり、時間帯によっては水抜きの音が近隣の方の迷惑になってしまったりということがあるかもしれません。
そのようなことを防ぐためにも、水抜きは明るい時間帯におこなうのがお勧めです。
勢いよく水が飛び出すことがあるので注意
エコキュートの水抜きでは、止水栓や給水栓、給湯栓を操作することがあります。
その際、状況によっては勢いよく水が飛び出すこともあるので注意してください。
あらかじめ手順をまとめたメモを作成したり、メーカーが公開している動画を再生したりしながら作業するのもお勧めです。
熱湯で火傷しないように注意
水やお湯に関しては、勢いよく飛び出す水だけでなく、熱湯にも気を付けてください。
エコキュートの貯湯タンク内には、設定温度次第ですが、約60~95℃のお湯が入っています。
飛び出した熱湯によって火傷することがあるため、水抜き時には注意しましょう。
慎重に焦らず一つひとつ確実におこなうようにするのが大切です。
冬期0度を下回るようなら水抜きはしない方が良い
エコキュートの水抜きは、少なくとも0度以上の気温がある環境でおこないましょう。
風呂配管の水抜きであれば良いですが、貯湯タンクやヒートポンプユニットの水抜きは、排水中に凍結するおそれがあります。
凍結してしまうとエコキュートの稼働に差し支えるため、とくに冬期の水抜きについては、注意が必要です。
冬期に水抜きをおこなう場合は、日中のような、できるだけ暖かい時間帯を選ぶようにしてください。
雪が積もるような寒冷地方の場合、外気温が0度以下になる時期を外して、水抜きのスケジュールを立てると良いでしょう。
劣化した部品は触らない
エコキュートを設置して10年近く経っているのであれば、劣化した部品には触らないように気を付けてください。
給水専用止水栓や排水栓といった栓類や、取り付けられたハンドル等が劣化している場合、無理に操作すると破損するおそれがあるためです。
排水が止まらなくなれば水道代がかさみ、業者に修理を依頼することになれば、修理費用もかかってしまいます。
部品の劣化が確認できる場合は、無理に触ろうとせず、業者に依頼してみてください。
数年おこなっていないのであれば業者に依頼も検討
「エコキュートを購入して数年経つのに、一度も水抜きをしたことがない……」という方もいるかもしれません。
長期間水抜きをしたことがない場合、一度作業をおこなっても完全に不純物や汚れを取りきれないケースも多々あります。
そのような数年水抜きをおこなったことがないというケースでは、業者に依頼するのも良いでしょう。
業者に依頼すれば貯湯タンクや配管周りがキレイになるだけでなく、点検も同時に受けられます。
その際に、何らかのメンテナンスや修理が必要になるケースもあります。
エコキュート本体の寿命は10年程度と言われていますから、状況に応じては修理ではなく、交換を検討しても良いかもしれません。
まとめ
エコキュート水抜きの重要性やメリット、実際の手順や注意点などについて詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。
エコキュートの水抜きは、清潔なお湯を使い、エコキュートの寿命を伸ばすために必要な作業です。
また災害時、エコキュート内の水を非常用水として使いたい方にとっても、水抜きは大切な作業といえます。
水抜き作業そのものは、取扱説明書やメーカーのホームページを見れば、初めてでも簡単にできるので、ぜひ挑戦してみましょう。
水抜きの頻度としては、半年から1年に一度程度が推奨されているので、スケジュールを立て、計画的におこなうことをお勧めします。
水抜きをおこなっても汚れが度々出るようであれば、修理や交換の時期に差し掛かっているかもしれません。
エコキュートの交換や買い替えの際は、ぜひ急湯デポにご相談ください。